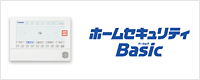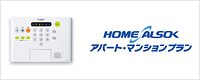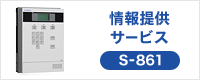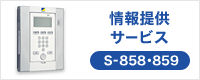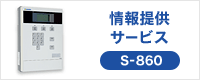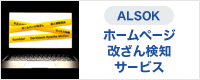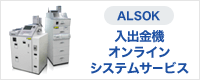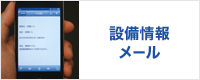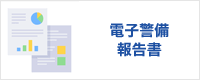家畜伝染病予防法とは?鳥インフルエンザや豚熱への予防と対策

農場を管理するうえで最も注意したいものの一つが、家畜伝染病です。家畜伝染病に罹患すると家畜の損耗や畜産物の生産性低下をもたらし、経済的にも大きな損失となってしまいます。
この記事では、家畜伝染病予防法の概要や、代表的な家畜伝染病である鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫の予防・対策方法などについて解説します。
目次
家畜伝染病予防法とは?
家畜伝染病予防法は、家畜が罹患する特定の伝染病(家畜伝染病)の発生・まん延を防止し、畜産の振興を図るための法律で、家畜伝染病に関する措置や輸出入検疫制度について規定するものです。
家畜伝染病の種類
家畜伝染病とは、家畜の感染症のうち罹患した場合の被害や影響が大きく、発生予防及びまん延防止措置を講ずる必要のある28種類の伝染性疾病を指し、牛や豚、鶏などの家畜別に家畜伝染病を定めています。
| 家畜伝染病の種類 | 対象家畜 |
|---|---|
| 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 牛肺疫 | 牛 |
| 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 水疱性口内炎 | 牛、馬、豚 |
| リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊 |
| 炭疽 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
| 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| ブルセラ症 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 結核 | 牛、山羊 |
| ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊 |
| ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) | 牛、馬 |
| アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) | 牛 |
| 伝達性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊 |
| 鼻疽 | 馬 |
| 馬伝染性貧血 | 馬 |
| アフリカ馬疫 | 馬 |
| 小反芻獣疫 | めん羊、山羊 |
| 豚熱 | 豚 |
| アフリカ豚熱 | 豚 |
| 豚水疱病 | 豚 |
| 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
| 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
| ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。) | 鶏、あひる、うずら |
| 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。) | 鶏、あひる、うずら |
| 腐蛆病 | 蜜蜂 |
また、農林水産省では、家畜伝染病の中でも特にまん延しやすく、総合的に発生の予防及びまん延防止のための措置を講ずる必要がある以下の8種類の伝染病疾病を、「特定家畜伝染病」に指定しています。
| 特定家畜伝染病の種類 | 対象家畜 |
|---|---|
| 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 牛肺疫 | 牛 |
| 口蹄疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
| 牛海綿状脳症 | 牛 |
| 豚熱 | 豚 |
| アフリカ豚熱 | 豚 |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
| 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら |
出典:e-GOV「家畜伝染病予防法 第二条」より一部抜粋
農林水産省「特定家畜伝染病防疫指針について」
家畜伝染病の発生による影響
家畜伝染病の発生によって、畜産農家の経済的な損失、食料の安定供給への影響、公衆衛生への影響などが起こり得ると考えられます。
家畜伝染病が確認された場合、家畜伝染病予防法に基づいて、殺処分の義務がある家畜は家畜防疫員の指示に従い、直ちにと殺しなければなりません。殺処分による畜産農家の経済的な損失は計り知れず、経営を左右する事態となります。
また、食料の安定供給にも大きな影響を与えます。本来であれば出荷されるはずの畜産物が出荷できなくなり、供給量の減少から価格が高騰し、影響が拡大すれば食料不足に陥るリスクも考えられるでしょう。
さらに、鳥インフルエンザや狂犬病など、一部の家畜伝染病は人への感染も確認されているため、公衆衛生上の影響も看過できません。
代表的な家畜伝染病①鳥インフルエンザ

ここからは、代表的な家畜伝染病である鳥インフルエンザについてご説明します。
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の伝染病です。家畜伝染病予防法では、ウイルスの型や病原性によって「高病原性鳥インフルエンザ」「低病原性鳥インフルエンザ」に分類されています。
特に高病原性鳥インフルエンザは危険性が高く、罹患した家畜の多くは命を失うとされています。それに対して低病原性鳥インフルエンザは、咳などの軽い呼吸器症状が出ることや産卵率が下がることがあり、場合によっては無症状のこともある病気です。
鳥インフルエンザの感染経路と予防法
鳥インフルエンザの感染経路として考えられるのは、鳥類の輸入、渡り鳥の移動、発生国からの肉・卵の輸入及び人の移動などです。すでに鳥インフルエンザが発生している国から、生きた鳥類や肉・卵を輸入することでウイルスが持ち込まれるケースがあります。しかし、これらの輸入時には検疫があり、鳥インフルエンザが発生した国からの輸入は停止措置が出されます。
渡り鳥が媒体の感染経路では、感染源となる個体との接触や、ウイルスが含まれる糞に汚染された水を介してウイルスがまん延するため、渡り鳥が家畜の群れに侵入しないよう対策を立てることが重要です。また、農場周辺の昆虫や小動物もウイルスを媒介することがあるため、こちらも対策が必要です。
人が原因の場合も、発症国に渡航していた人、渡り鳥やその糞に接触した人、ウイルスが発生した場所にいた人を農場に近づけないことで、ウイルスの持ち込みを予防できます。
飼育している鳥が鳥インフルエンザに感染してしまった場合の対応
鳥インフルエンザが発覚した場合、畜産農家は家畜伝染病予防法に基づき、農場で飼育されている該当家畜の殺処分、焼却または埋却を行います。それに加えて、消毒や移動制限など必要な防疫措置を実施しなければなりません。これらの防疫処置は鳥インフルエンザのまん延を防ぎ、感染した家畜の精肉や卵が市場に出回るのを防ぐことが目的です。
代表的な家畜伝染病②豚熱
鳥インフルエンザと並んで代表的な家畜伝染病が、豚熱です。
豚熱とは
豚熱は豚やイノシシが感染する伝染病で、CSFとも呼ばれています。高い致死率と強い感染力が特徴です。豚熱に感染すると、発熱・下痢・便秘・食欲不振・呼吸障害などの症状が現れますが、特徴的な症状がないため発見が遅れやすい病気です。
人には感染せず、豚熱に罹患した豚の肉を食べても人体に害はないとされていますが、農場にまん延すると多くの豚が死に至ってしまい、経済的に大きな打撃となります。
なお、よく似た伝染病にアフリカ豚熱(ASF)がありますが、豚熱とはまったく異なる病気です。
豚熱の感染経路と予防法
豚熱の感染経路は、感染した豚やイノシシの涙・糞尿・唾液などとの接触感染といわれています。豚熱を予防するには、関係者以外の農場への立ち入りを制限する、出入口での消毒を徹底する、野生のイノシシが侵入しないよう柵を設置するなど、日々の管理が必要です。
特に野生のイノシシ対策は重要なため、猟友会や自治体と連携を図り、周辺のイノシシの感染状況を把握しましょう。イノシシの死骸を発見した際には、自治体もしくは家畜保健衛生所に報告し、速やかに処理するようにします。
また、豚熱には有効なワクチンがあり、農林水産省が指定する地域に限り豚熱ワクチンの接種を受けられます。
飼育している豚が豚熱に感染してしまった場合の対応
鳥インフルエンザと同様、豚熱の感染が確認された場合は、家畜伝染病予防法に基づいた防疫措置を実施しなければなりません。農場で飼育しているすべての豚を殺処分したうえで、徹底した消毒作業など、感染拡大を防ぐための迅速な対応が求められます。
代表的な家畜伝染病③口蹄疫

最後に、口蹄疫について解説します。
口蹄疫とは
口蹄疫は、牛・めん羊・山羊・豚などの家畜や、シカなどの野生動物が罹患する伝染病です。感染した動物には、発熱・泡状のよだれ、口内や蹄の水ぶくれ、足の引きずりなどの症状が見られます。致死率は高くないものの、偶蹄類動物(ほ乳類の偶蹄目に分類される蹄が偶数本ある動物。牛、豚、山羊、羊、鹿、らくだなど。)に対する感染力が非常に強く、牛から豚、さらに山羊など、他の動物へと感染が連鎖する可能性があります。
なお、日本では2010年に宮崎県で発生した事例を最後に、口蹄疫の感染例は報告されていません。殺処分や移動制限など適切に行った結果、2012年に口蹄疫清浄国として認定されました。
口蹄疫の感染経路と予防法
口蹄疫の感染経路は、感染した動物との接触や、ウイルスに汚染された水・肉・飼料(稲わら)、ウイルスが付着した靴を履いた人の移動などです。
日本では2010年以降口蹄疫は報告されていませんが、中国や韓国など近隣諸国では継続的に発生しているため、人や物を媒介して日本にウイルスが侵入するリスクは非常に高い状況です。海外からウイルスを持ち込ませないためにも、畜産農家には関係者以外の立ち入り禁止や、出入口での靴底の徹底的な消毒、車両の消毒、発生国への渡航中止などの対策が求められます。
飼育している牛が口蹄疫に感染してしまった場合の対応
基本的には他の家畜伝染病と同じ対応で、感染が発生した農場の対象家畜はすべて殺処分しなければなりません。泡状のよだれを垂らしている、口内や蹄に水ぶくれがあるなど、感染が疑わしい場合にはすぐに獣医師や家畜保健衛生所に通報しましょう。
家畜伝染病における基本的な予防法
家畜伝染病を防ぐには、基本的な予防法を実行することが重要です。
衛生管理の徹底
家畜伝染病を防ぐうえで大切にしたいポイントが、病原体を持ち込まない・区域内で拡げない・区域外へ持ち出さないことです。農場に出入りする関係者全員の協力のもと、靴底や物品の消毒、使用済み手袋や退出時の手指の消毒、車両の消毒、新規導入家畜の一時隔離などを徹底することで、適切な衛生管理につながります。
なお、農林水産省のページには「飼養衛生管理基準ガイドブック」というガイドラインが掲載されており、牛・豚・鶏など家畜別の管理基準を確認できます。
衛生管理の状況を定期的に報告
畜産農家は、飼育している家畜の数や衛生状況に関して、都道府県に毎年定期報告をしなければなりません。具体的には、関係法令の遵守状況、地域の畜産農家との協力状況、消毒記録の作成・保管状況など、さまざまな項目について報告義務があります。普段から衛生管理の意識を高め、適切に管理することが重要です。
伝染病から家畜を守るALSOKサービス
ALSOKでは、伝染病から家畜を守るために役立つサービスをご提供しております。
家畜防疫対策支援サービス
ALSOKの家畜防疫対策支援サービスでは、家畜伝染病発生時のまん延防止をサポートしております。防疫活動に必要な物資の調達だけでなく、消毒ポイントの設営・運営、通行制限のかかった道路における交通誘導業務まで、ワンストップでご提供します。農場関係者はご自身の業務に専念していただけます。
ALSOKの関連商品
防犯カメラ・監視カメラサービス
ALSOKの防犯カメラ・監視カメラサービスは、簡単な操作で昼夜関係なく鮮明な映像を記録し、部外者による畜舎への出入りを監視するだけでなく、家畜の様子を撮影・録画し、離れた場所から確認することができます。多種多様なラインナップを取り揃えており、農場の規模やお客さまのご要望に合わせて最適なプランをご提案します。
ALSOKの関連商品
機械警備システム
最先端の機械警備を活用した「ALSOKガードシステム」では、不審者の侵入監視はもちろんのこと、各種センサーによって火災の発生や設備(照明・空調・シャッターなど)の異常を遠隔監視し、万が一異常が発生した場合にはALSOKが現場へ駆けつけて適切に対処、状況に応じて各関係機関と連携いたします。
ALSOKの関連商品
まとめ
家畜伝染病を予防するには、病原体を持ち込まない・区域内で拡げない・区域外へ持ち出さないことが基本です。
しかし、予防を徹底していてもリスクをゼロにすることは難しく、家畜伝染病が発生した場合は、家畜伝染病予防法にしたがって該当家畜はすべて殺処分し、感染拡大防止のために消毒や移動制限などにも対応する必要があります。
家畜伝染病対策にお悩みの場合は、ぜひお気軽にALSOKにお問い合わせください。