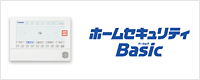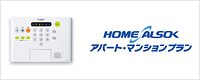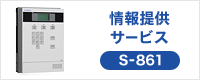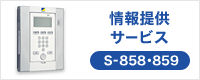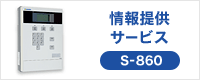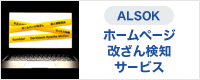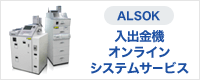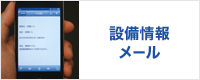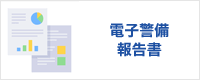小学校におけるリスクマネジメントとは?危機管理マニュアルを含めた事前対策の重要性

小学校には、自然災害の発生や校内での事件・事故、校内への不審者の侵入などさまざまなリスクがあります。児童が安心して学校生活を送るには、日ごろからリスクマネジメントを徹底してトラブルを未然に防ぎ、万が一の事態に備えておくことが重要です。
この記事では、小学校におけるリスクマネジメントについて、事前、発生時(初動)、事後の危機管理に分けて解説します。危機管理マニュアルの見直しや事前対策の重要性を理解し、児童の安全を確保できる体制を整えましょう。
目次
小学校における主なリスク

小学校における主なリスクには、大きく分けて「自然災害リスク」と「事件・事故のリスク」の2種類があります。
自然災害リスク
自然災害リスクとして考えられるのは、地震・火災、風水害(台風・豪雨)・津波・火山噴火などです。
地震・火災
地震大国である日本では、大規模な地震発生のリスクを常に考えておく必要があります。今後30年以内に首都直下型地震が起こる確率は70%程度、南海トラフ巨大地震が起こる確率は80%程度だといわれており、いつ大地震が発生してもおかしくない状況です。
また、地震にともなう火災や津波の発生など、二次災害も想定されます。
風水害(台風・豪雨)・津波・火山噴火など
台風や集中豪雨などの風水害も毎年各地で発生しています。台風や豪雨は突如発生する地震よりも予想が可能なため、事前の判断など計画的な対応が求められます。風水害発生時には、洪水や高潮、崖崩れなどのリスクもあります。
また、近くに火山がある場合は火山噴火にともなう避難計画の作成が必要です。津波は地震発生時だけでなく火山や土砂災害の影響により発生する可能性もあります。
事件・事故のリスク
事件・事故のリスクとして挙げられるのは、不審者の侵入、校内でのケガや急病などです。
不審者の侵入
不審者が侵入してきた場合、児童に何らかの危害を加える可能性があります。小学校への不審者侵入による事件は相次いで発生しており、児童や教職員の身を守るための危機管理対策が急務となっています。
校内でのケガ・事故
校内でのケガや、給食での食物アレルギーや食中毒、授業中の体調不良などのリスクが考えられます。また、登下校中のケガや交通事故のリスクもあります。
危機管理マニュアルの役割と重要性
小学校における自然災害や事件・事故のリスクに備えるため、学校保健安全法において全学校で危機管理マニュアルの作成が義務づけられています。
文部科学省では、危機管理マニュアル等の作成の手引き、評価・見直しに関するガイドラインをまとめています。
文部科学省
学校の危機管理マニュアル作成の手引
学校の「危機管理マニュアル等」の評価・見直しガイドライン
学校の「危機管理マニュアル等」の評価・見直しガイドライン 学校向け参考リーフレット
危機管理マニュアルの重要性
危機管理マニュアルは、小学校で起こりうるリスクを想定して、事前の対策や事後の対応フローなどについて定めたものです。緊急時に教職員が取るべき行動を明確にし、児童を被害から守るためにも、危機管理マニュアルは非常に重要なものです。
危機管理マニュアルを作成するだけでなく、教職員が内容を理解し保護者や地域住民にも周知・共有することで、適切な対応が可能になり児童の安全確保につながります。また、環境の変化や他校での取り組み事例などをもとに随時見直すことも重要です。
危機管理における3つの段階
文部科学省のガイドラインでは、危機管理マニュアルを見直す際に、以下3つの段階に分けて考えることが推奨されています。
1.事前の危機管理
リスクの把握、事故・災害等の未然防止対策、事故・災害等の発生に備えた対策の3つの観点から危機管理を考える。
2.発生時(初動)の危機管理
事故・災害等の発生時の初動をフロー図で明示し、教職員が訓練・研修で身につけられるようにする。
3.事後の危機管理
様々な事態への対応、復旧・復興への対応、事故の調査、再発防止策の取り組みなど、事後の対応について示す。
以下では、3段階それぞれの内容について詳しく見ていきます。
事前の危機管理
事前の危機管理の段階には、以下の内容を盛り込みます。
リスクの把握
どのような事故・災害リスクがあるかを把握するには、まず以下のような観点から学校の状況を総合的に整理する必要があります。
- 学校の立地、規模
- 登下校方法、登下校時間、通学範囲
- 生徒、教職員の状況(在籍する生徒数、教職員数) など
そのうえで、発生が想定される次のようなリスクを具体的に洗い出します。
- 傷病の発生(熱中症、階段からの転落など)
- 犯罪被害(不審者の侵入、校内不審物、近隣での事件発生など)
- 食物アレルギー・食中毒
- 交通事故
- 災害(地震、津波、火災、台風、大雨、洪水、土砂災害) など
危機の未然防止対策
リスクを把握したうえで、危機を未然に防止するための体制を整えます。全教職員の役割を明確にし、学校全体で安全な環境整備に取り組めるようにしましょう。
また、事故・犯罪・災害などへの具体的な対策も記載しておきます。
- 不審者対策:校門の施錠、来校者管理の方法、防犯カメラ・警備システムの導入
- 食物アレルギー対策:給食管理体制の見直し、教室ごとのルール決め
- 災害対策:避難訓練、備蓄品の準備と管理、天井材や外壁の点検、備品・本棚の固定 など
危機発生に備えた対策
次に、危機発生時における教職員の招集方法や、対策本部の設置基準、保護者や関係機関との連絡体制など、緊急時の体制整備を整えます。また、災害別の避難場所などを決めた避難計画を作成し、避難訓練を実施することも重要です。
発生時(初動)の危機管理

発生時(初動)の危機管理では、実際に危機が発生した際にどのような行動を取るかを決めます。
自然災害発生時
台風・大雨などの気象災害が発生した場合は、休校の判断、周辺の河川氾濫や土砂災害の危険性の把握、近隣学校との情報共有などが必要になります。
火災発生時については危機管理マニュアルではなく、基本的には「消防計画」に則って対応します。
また、地震の発生時には、次のように段階的に避難することが重要です。
一次避難:揺れを感知したと同時に、身の安全を確保する避難
二次避難:校庭など、安全な場所への避難
三次避難:火災や津波などの危険が迫っている場合に行う、高台など校外への避難
火災・気象災害・地震それぞれの初期対応についても、フローチャートで明示しておくことで円滑な対応につながります。
犯罪被害発生時
校内への不審者の侵入、犯罪予告、登下校時の不審者など、犯罪被害の発生時にどのような対応を取るのかも決めておきます。こちらも、次のような要素を盛り込んだフローチャートを作成しましょう。
- 不審者の判別方法
- 不審者と判明した場合の対応
- 対応上の注意点(2人以上で対応する、相手に背を向けない、不審物に触らない)
- 119番、110番への通報、学校設置者等への連絡 など
傷病者発生時
学校内での事故・熱中症・食物アレルギーなど、傷病者が出た場合には迅速かつ的確に手当てし、関係機関に連絡するなどの対応が必要です。緊急時でも冷静に対処するために、取るべき行動をまとめたフローチャートの作成が推奨されています。フローチャートには、以下のような内容を簡潔に盛り込みましょう。
- 発見者の役割(症状確認、応急処置、協力要請)
- 複数の教職員による対応(救急車の要請、AED手配、他の児童への配慮)
- 119番、110番への通報
- 保護者への連絡
- 学校設置者等への連絡 など
ALSOKの関連コラム
事後の危機管理
事後の危機管理の段階では、主に以下の内容を決めます。
事後(発生直後)の対応
まず行うべきことは、児童の安否確認です。安否確認の方法や、安否確認を実施する基準も明確に定めておくとよいでしょう。災害時にはインフラが混乱する可能性もあり、普段の連絡手段が使用できないケースも想定されます。貼り紙や伝言システムなど、緊急事態に備えた安否確認手段を考えておくことが必要です。
状況に応じて、集団下校や保護者への引き渡しを行う場合もありますが、被災した児童は精神状態が不安定なことも考えられます。保護者へ連絡する際は「事実や状況を伝える」だけではなく、児童に寄り添った対応を取ることが重要です。また、報道機関に被災情報を公表する前には保護者の承認を得るなどの配慮も必要です。
心のケア
学校保健安全法では、事故・災害時に危害を受けた児童や、関係者の心身のケアを行うことが定められています。児童だけでなく、教職員の心のケアも行う必要がある点に留意が必要です。心身の健康状態の確認、トラウマ反応の確認、保護者との連携、医療機関との連携など、心のケアに必要な対応についてまとめておきましょう。
調査・検証・報告・再発防止策
学校設置者等への報告手順、内容、様式なども危機管理マニュアルに記載しておきます。また、再発防止に向けた調査を行うために、調査の対象範囲や調査方法、記録の取り方まで決めることが重要です。調査の結果、課題や改善点が見つかった場合は再発防止策を検討します。
小学校のリスクマネジメントに役立つALSOKのサービス
ALSOKでは、小学校のリスクマネジメントに役立つサービスをご提供しております。
【災害への対策】
BCPソリューションサービス
ALSOKでは、BCP(事業継続計画)の策定をサポートしております。マニュアル作成から全校での共有、対策の実施、講習や訓練など、定着化まで一貫して支援します。
また、火災種別に適応する各種消火器も取り扱っております。消火器の定期点検や入れ替えもALSOKにお任せください。
ALSOKの関連商品
防災備蓄品(管理含む)
ALSOKでは、防災備蓄品の販売だけでなく、備蓄品の期限管理や棚卸、回収調整などを行う「災害備蓄品マネジメント支援サービス」をご提供しております。万が一の際に、災害備蓄品・災害対策用品を適切に使用できるようALSOKが一元管理いたします。
ALSOKの関連商品
安否確認サービス
災害などの緊急時に、教職員・児童の状況をただちに把握するための安否確認システムもご提供しています。
災害発生時にALSOK安否確認サーバからすぐ安否確認メールが自動送信され、効率的に教職員や児童の保護者とコンタクトをとることが可能です。
また、一斉送信される自動送信メールや通知に加え、管理者が任意で特定の関係者に緊急連絡を行える仕組みも備えているため、何らかのトラブルが発生した際にも確実な情報伝達を可能にしています。
ALSOKの関連商品
【事件や事故への対策】
機械警備
ALSOKの機械警備では、侵入者の感知やリアルタイムでの画像監視・音声警告が可能です。また、火災の発生や設備の異常も24時間監視し、異常事態が発生した際にはALSOKが駆けつけ一次対応します。状況に応じて各関係機関と連携し、被害の拡大防止と二次被害の防止に貢献します。
ALSOKの関連商品
防犯カメラ・監視カメラサービス
ALSOKの防犯カメラ・監視カメラサービスは、施設やお客様のご要望に合わせて多種多様なラインナップから最適なプランをご提案します。昼夜を問わず高画質な映像を記録でき、シンプルなオペレーションで誰でも簡単に操作、離れた場所からでも映像を確認することができます。工事費込みのお得なパッケージプランもご用意しています。オプションサービスで、ALOSKのデータセンターで録画映像を保管するクラウドサービスも利用可能です。
ALSOKの関連商品
ALSOKの関連コラム
AED
学校での活動中に突如心停止を起こした児童や教職員がAEDによって助かった事例が報告されており、今や学校へのAEDの設置は不可欠になっています。ALSOKではお客様のニーズに合わせて、幅広いラインナップから最適なAEDをご提案します。徹底したAED本体や消耗品の管理体制を構築し、講習サポートも実施しているため導入後も安心です。
ALSOKの関連商品
ここまでご紹介したサービス以外にも、ALSOKでは防犯・防災面でのアドバイスが可能です。施設の状況や課題に合わせて、適切なプランをご提案します。
また、啓蒙活動「ALSOKあんしん教室」も開催しており、児童に防犯意識を持ってもらうための「防犯授業」、AEDの役割や心肺蘇生法について学べる「救急救命授業」などを行っています。
ALSOKの啓蒙活動
まとめ
小学校への不審者の侵入や事故・災害の発生など、さまざまなリスクに対処するには、危機管理マニュアルの見直しを行うなど、リスクマネジメントを徹底することが重要です。
児童が安心して学校生活を送れる環境を整えるためにも、リスクマネジメントによってトラブルを未然に防ぎ、万が一の事態には迅速・適格に対応できるように備えておきましょう。