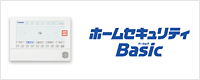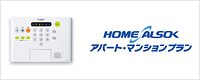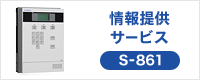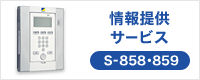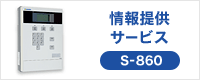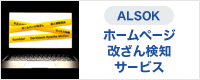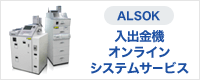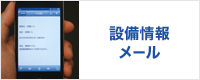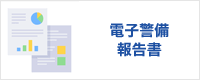9月の旬の食材を堪能しよう!旬を迎える秋の味覚をご紹介

読書の秋、スポーツの秋といった「〇〇の秋」という言葉はいくつかありますが、もっとも人気があるのはやはり「食欲の秋」ではないでしょうか。
9月に入るとたくさんの食材が旬を迎え、秋の味覚が楽しみになります。季節の変わり目であるこの時期は、気温差があり風邪をひきやすいため免疫力の強化が期待できる旬の食材を積極的に摂りたいところです。
そこで本コラムでは、9月に旬を迎える魚や野菜、果物をご紹介します。
目次
9月は食欲の秋!旬の食材を堪能しよう
9月に入ると、暑かった夏から少しずつ気温が落ち着いてきます。この時期は「十五夜」「重陽(ちょうよう)の節句」など、食に関する秋の行事が多いのが特徴です。「食欲の秋」という食べる楽しみが増す言葉もあり、「おいしいものが多い時期」とイメージする方も多いのではないでしょうか。
9月に旬を迎える食材はたくさんあります。今回は、魚やきのこ類・いも・果物など、秋の味覚で思い浮かぶ旬の食材をいくつかピックアップして、特徴や調理法をお伝えします。
9月が旬の食材は?

9月が旬の食材として、以下のものが挙げられます。
- カツオ
- サンマ
- アサリ
- かぼちゃ
- 里芋
- 舞茸
- 銀杏
- 巨峰・ピオーネ
- 梨
- 栗
9月が旬の魚
カツオ
カツオは、春と秋に旬を迎えます。秋に穫れるカツオは「戻りカツオ」ともいいます。三陸沖から南下してくるため、栄養をたっぷりと蓄えていて脂がのっているのが特徴。「トロカツオ」や「脂カツオ」と呼ぶこともあります。お刺し身で食べるとより一層、カツオのうま味を感じられます。
栄養素
カツオには、体内の代謝を促進してくれるビタミB群が豊富に含まれています。ただし、含まれているビタミンは水溶性ビタミンといって、尿として排出されやすいため、他の食材との食べ合わせで体への吸収率を上げると良いでしょう。
ビタミンB1の吸収率をアップするアリシンを含む玉ねぎやにんにくと合わせると吸収されやすくなります。他にも、カツオには体力や免疫力を支えるたんぱく質や動物性鉄分といった栄養素も含まれています。貧血気味の方や体が疲れている方にはおすすめの食材です。
選び方
美味しいカツオは、血合いは鮮やかなえんじ色で、身は透き通ったような鮮やかな赤が特徴です。また、皮と身の間に脂が乗っている場合、皮を剥くと表面が脂で白っぽいピンクの色になっています。
サンマ
サンマは漢字で書くと「秋刀魚」となり、文字の通り秋を代表する魚です。夏から秋にかけて、サンマは北から南下していきます。8月の末から北海道で水揚げが開始され、徐々に三陸沖へと移動してきます。三陸沖は親潮と黒潮がぶつかりエサが豊富なことから、9~10月に穫れるサンマは脂がのっているのが特徴です。
また、この時期にしか生サンマは獲れないため、新鮮なサンマを食べられるのは秋だけ。塩焼きはもちろん、お刺し身でもおいしくいただけます。
栄養素
サンマには、DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペタンエン酸)という必須脂肪酸が豊富に含まれています。この必須脂肪酸は、血液の流れをよくする効果が期待でき、生活習慣病の予防に役立つといわれています。
選び方
サンマは、頭から背中にかけて盛り上がっていて、厚みのあるものは脂が乗っている証拠です。黒目のまわりが濁っておらず、透明で澄んでいるのも良いとされています。魚は内蔵から悪くなることから、お腹が硬いものは、新鮮なのでチェックしましょう。
アサリ

潮干狩りは春のイメージがありますが、実は、秋も旬の時期です。冬を除いて通年産卵をしますが、春と秋の産卵前は特においしさのピークを迎えます。アサリには、うま味成分であるグリコーゲンやコハク酸がたっぷり。旬を迎えるアサリは、さらにそのうま味成分がアップしています。
旬のアサリは栄養がたっぷりなので、煮汁と一緒にとれるクラムチャウダーや味噌汁などの料理がおすすめです。
栄養素
アサリには、鉄分やビタミンB12、亜鉛が多く含まれています。鉄分やビタミンB12は貧血予防に役立ち、亜鉛は免疫力強化をサポートしてくれる成分です。貧血気味な方は、積極的にアサリを摂取すると良いでしょう。
選び方
アサリは、貝殻の口が固く閉じていて、殻の表面につやがあるものが新鮮な証拠です。むき身の場合は、身に張りがあり、透明感のあるものを選びましょう。
9月が旬の野菜・きのこ
かぼちゃ
かぼちゃは、日本かぼちゃ・西洋かぼちゃ・ペポかぼちゃの3種類に分かれます。現在、日本では甘みの強い西洋かぼちゃが主流です。
かぼちゃは冬至に食べる習慣があるため、旬の時期は冬をイメージするかもしれません。実は、かぼちゃは夏から秋にかけて旬の時期を迎えます。冬にかぼちゃを食べるのは、貯蔵ができるからです。カットしていないかぼちゃであれば、冷暗所で1~2カ月の保存が可能です。
かぼちゃはサラダにしても良いですし、コロッケにするとより甘みが引き立ちますよ。
栄養素
かぼちゃには、β-カロテン、ビタミンC・Eが豊富に含まれています。これらの成分が相乗的に働き、免疫力を強化したり細胞の老化を予防する効果につながるといわれています。
選び方
丸ごと1個のかぼちゃの場合、ずっしりと重みがあり、緑色が濃いものを選びましょう。ヘタのまわりがくぼんでいたり、コルクのように乾燥していたりするものは、完熟している傾向にあります。
カットされているものを選ぶ場合は、種がしっかりと詰まっていて、肉厚で色が鮮やかなものを選ぶようにしましょう。
里芋

里芋は、9月から旬の時期を迎えます。基本的にはでんぷん質が多い里芋ですが、芋の中でも水分が多いためカロリーが低めです。
そんな里芋は、煮物にするのがおすすめ。シンプルに里芋だけの煮物も良いですし、イカと一緒に煮込むのも良いでしょう。
栄養素
ぬめりが特徴の里芋ですが、そのぬめりはガラクタンという食物繊維です。ガラクタンには腸内環境を整えたり、血糖値やコレステロール値の上昇を抑制したりする効果が期待できます。
選び方
里芋は、皮が乾燥しすぎていなく、しっとりと湿っているものが新鮮な証拠です。さらに皮のしま模様がくっきりと見えていて、固いものを選びましょう。
また、表面に泥がついたまま売られているものは風味が良い傾向にあります。
舞茸
昔は舞茸を人工栽培することができず、また天然の舞茸を見つけることも貴重なことでした。そのため、「見つけると舞うほどうれしい」ということから、舞茸と名付けられています。現在は人工栽培も可能になり、気軽に食べられるようになったきのこです。
舞茸は、水溶性の栄養素が多いため、スープや味噌汁に入れるとうま味と一緒に栄養も逃さず取り入れられます。舞茸と油揚げを入れた炊き込みご飯にして楽しむのもおすすめです。
栄養素
舞茸には、カルシウムの吸収をサポートするビタミンD、ビタミンB2やナイアシンなどのビタミンB群、亜鉛が豊富に含まれています。
選び方
舞茸は、カサの色がはっきりとしていて光沢があり、肉厚なものを選びましょう。古くなると水分が蒸発します。そのため、袋やパックの内側に水滴がつくほど蒸発している舞茸は、袋詰されてから日が経っているものが多いです。蒸発していないか、表面が乾燥していないかもチェックしましょう。
また、弾力も大切です。鮮度が落ちてくるとハリがなくなり柔らかくなってくるため、弾力があるかも確認することをおすすめします。
銀杏
イチョウの木からとれる銀杏も秋の味覚の1つ。銀杏は、塩と一緒に紙袋に入れて電子レンジで加熱するだけでシンプルに味わえます。味にややクセがあるので、茶わん蒸しに入れて味のアクセントにするのも良いですね。
栄養素
銀杏には、β-カロテンやビタミンCを含んでいるため、免疫力のアップに期待できます。ただし、メチルピリドキシンという物質が含まれており、銀杏を食べ過ぎると食中毒を起こす可能性があるため注意が必要です。
選び方
殻付きの場合は、表面がよく乾燥していて白いもの、振っても音がしないものを選ぶようにしましょう。
9月が旬の果物
巨峰・ピオーネ

巨峰やピオーネといったぶどうも9月に旬を迎えます。巨峰とピオーネは、ぶどうの品種のなかでも、大粒なのが特徴です。大きな粒のため、見た目と食べ応えも抜群。糖度も高く、みずみずしい果汁も魅力です。ぶどうの中でも人気なことから、ぶどうの王様ともいわれています。
栄養素
巨峰とピオーネには、体のエネルギーになるブドウ糖が豊富です。その他に、健康を維持するために必要なビタミン群や塩分の排出を助けるカリウムなどが含まれます。また、抗酸化作用などに期待できるポリフェノールも豊富です。
選び方
巨峰・ピオーネは、軸が緑色で、弾力があり水気のあるものを選びましょう。また、果皮が黒々していて、粒が大きくしっかりしているものが良いとされています。
表面についた白い粉は、「ブルーム」と呼ばれ、ぶどう本来の天然成分です。この白い粉は、新鮮な証拠なので、たくさんついているものを選ぶことをおすすめします。
梨
梨も夏頃から秋にかけて旬を迎えます。品種によって旬の時期に違いがあり、冬に旬を迎える品種もあります。9月に旬のピークを迎えるのが「豊水」という品種です。果肉がやわらかく、果汁がたっぷりなのが特徴です。
栄養素
梨には、カリウムが多く含まれています。カリウムは、ナトリウム(塩分)の排出を促し血圧を下げる働きがあります。カリウムが不足すると体がむくみやすかったり、手足のだるさにつながることがあります。9月は秋ですが、まだまだ気温が高く暑い季節です。暑いとカリウムが失われるため、積極的に摂取すると良いでしょう。
選び方
梨は、形が良くて果皮に張りがあるもの、ずっしりと重みがあるものが良いとされています。また、色ムラや傷がないかもチェックしておきましょう。表面のざらざら感は、熟すにつれてなくなってきます。すぐに食べたいたときは、表面がつるつるになっているものを選びましょう。
栗
秋の味覚の代表格ともいえる栗は、9月頃に旬を迎えます。栗は、野菜ではなく木になる果実です。縄文時代の遺跡から栗が多く出土していることから、長い間日本で親しまれてきた食材といえます。栗ご飯や甘露煮にして楽しむのがおすすめです。
栄養素
栗は炭水化物が多く、ビタミンB1とB2を多く含んでいます。ビタミンB1は糖の代謝、ビタミンB2は脂質の代謝をサポートしてくれます。
選び方
栗を選ぶ際は、皮に光沢やツヤがあるか、ずっしりと重みがあるものは水分を含んでいてみずみずしさがありおいしいです。また、ふっくらとしていて、1粒が大きいかも確認しましょう。皮の底がきれいな白色で大きいものがおすすめです。また、虫食い穴がないかもチェックしておくと安心です。
秋から増え始める空き巣
空き巣が増える時期とは
おいしい食材を楽しめる秋ですが、実は空き巣などの犯罪に注意が必要な季節です。泥棒や空き巣による侵入窃盗は、秋から冬にかけて増えていきます。これは、日没時間が早くなりひと目につきにくくなるのが原因のひとつです。また、秋はレジャーシーズンでもあり冬もイベントが多くあるため、家を留守にする方が増えるのも一因です。
空き巣被害を防ぐための防犯対策
空き巣被害を防ぐには、施錠を忘れずに行うという基本的な対策に加え、防犯対策を行う必要があります。少しの時間留守にする際でも必ず窓やドアの鍵は締めるようにしましょう。また、庭や玄関付近に死角があると隠れやすいため、空き巣が入りやすい傾向にあります。草木は、定期的にお手入れをしたり、死角となる位置に物を置いたりしないようにしましょう。
空き巣は窓から侵入するケースも多いため、防犯フィルムや補助錠、防犯カメラといった防犯アイテムを利用するのも効果的です。
空き巣の詳しい防犯対策に関しては以下コラムも参考にしてみてください。
空き巣から家を守るにはALSOKのホームセキュリティ
住宅の防犯対策として、ホームセキュリティの導入も効果的です。ALSOKでは、留守中のご自宅を泥棒・空き巣から守る「ホームセキュリティ」をご提供しています。
ALSOKのホームセキュリティには、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つがあります。セルフセキュリティでは、月額 990円(税込)からとお手軽にホームセキュリティを実現でき、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。オンラインセキュリティでは、異常発生時には自動でガードマンが駆けつけます。
また、スマホを持っているだけで、自動で警備解除が可能なスマホゲートもご用意。外出時はワンタッチで警備を開始でき、外出の前にはスマホの持ち忘れもお知らせしてくれるため、安心してでかけることができます。
大切な家を守るためのホームセキュリティの導入を考えている方は、手軽に防犯対策ができるALSOKの「HOME ALSOK Connect」を検討してみてはいかがでしょうか。