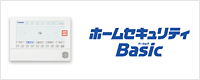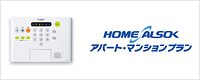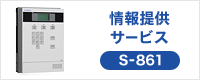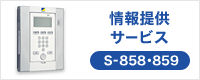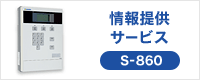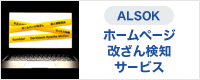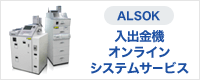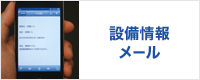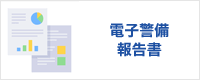乳幼児健診はいつ?赤ちゃんの健診スケジュールや内容を解説

赤ちゃんが生まれると、身体の発育状況や栄養状態、心身の異常の早期発見など、乳幼児の健康状態を把握し、育児の相談や専門相談につなげるために定期的に乳幼児健診が行われます。初めて乳幼児健診を受ける方、これから赤ちゃんを出産予定の方は、乳幼児健診はいつ受けるのか、どのような内容なのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、乳幼児健診のスケジュールや内容、よくある疑問についてご紹介します。
目次
乳幼児健診とは?

乳幼児健診は、正しくは「乳幼児健康診査」といい、赤ちゃんや就学前までの子どもが健やかに育っているかどうかを確認するために、自治体ごとに行われる健診のことです。
乳幼児健診では、発育・栄養状態の確認や病気の兆候はないかなどをチェックします。また、成長や健康の確認だけではなく、ママ・パパが育児の面で気になることを相談できる場でもあります。
年齢に応じて栄養指導・歯科指導なども行われ、離乳食についてわからないことや歯磨きの仕方などを教えてもらうことも可能です。
乳幼児健診のスケジュール
乳幼児健診はいつ実施されるのでしょうか。自治体にもよりますが、ここでは一般的な健診スケジュールの例をご紹介します。
| 健診名 | 通知 | 健診内容 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 1カ月児健康診査 | 退院時に病院・産院から通知 | 身体測定・診察・育児相談 | 1カ月児 |
| 3~4カ月児健康診査 | 2か月頃に通知 | 身体測定・診察・育児相談 | 3~4カ月児 |
| 6~7カ月児健康診査 | 3~4カ月健診の際に通知 | 身体測定・診察・育児相談 | 6~7カ月児 |
| 9~10カ月児健康診査 | 3~4カ月健診の際に通知 | 身体測定・診察・育児相談 | 9~10カ月児 |
| 1歳6カ月児健康診査 ※法定健診 |
1歳5カ月頃に通知 | 身体測定・内科診察・ 歯科診察・育児相談 |
1歳6カ月~2歳未満児 |
| 3歳児健康診査 ※法定健診 |
3歳になる前月に通知 | 身体測定・内科診察・ 歯科診察・尿検査・ 育児相談 |
3歳1カ月~4歳未満児 |
乳幼児健診は子どもの月齢に応じた発達状況を確認するため、月齢に合わせた健診を受けます。
生後1カ月の1カ月児健康診査は、母体の回復状態を診るための産後健診と合わせて、出産した病院や産院で行われます。
母子保健法により「1歳6カ月」と「3歳」の健診は法的義務とされており、実施は任意ですが、「3~4カ月健診」もほとんどの自治体で実施されています。他の健診はお住まいの地域によって乳幼児健診を行う時期が異なります。
また、自治体から指定されていない年齢でも、任意で乳幼児健診を受けることが可能です。
乳幼児健診の内容
自治体によって健診の対象時期や内容は異なりますが、一般的にどのようなことを診察するのかを月齢別にご紹介します。
1カ月児健康診査
1カ月児健康診査では、授乳量や睡眠量、健康状態の確認、身体測定や原始反射の確認、医師による診察などが行われます。
赤ちゃんと過ごす最初の1カ月が過ぎ、色々と不安に感じていることや分からないこともあるでしょう。気になることがあれば、医師や助産師に何でも相談しましょう。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 運動機能・感覚機能・反射の確認
- 先天異常の有無、その他の疾病及び異常の有無
- 育児上問題となる事項の確認・育児相談
多くの産院では、赤ちゃんのビタミンK不足による出血を防ぐため、ビタミンK2シロップの投与が行われます。
また、病院・産院によっては、出生後に受けた先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング)・新生児聴覚検査の結果説明がある場合もあります。
3~4カ月児健康診査
3~4カ月児健康診査では、身体測定、医師による診察を実施し、首のすわり具合など身体機能の発達状況が順調か、先天性の異常がないかを確認します。
子育てに関して気になることがあれば医師や保健師に相談しましょう。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 運動機能の発達状況
- 精神発達の状況
- 神経系・感覚器系の異常の有無
- 血液や皮膚の疾病の有無
- 股関節の異常の有無
- 循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系の疾病の有無
- 先天異常の有無
- その他の疾病及び異常の有無
- 生活リズムや母の心身状態など、育児環境などの確認や育児相談
6~7カ月児健康診査
6~7カ月児健康診査では、身体測定、医師による診察を実施します。寝返りやお座りなど身体機能の発達状況や、先天性の異常がないかの確認が行われます。
子育てに関して気になることがあれば医師や保健師に相談しましょう。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 離乳食の進み具合の確認
- 運動発達の状況
- 精神発達の状況
- 神経系・感覚器系の異常の有無
- 血液や皮膚の疾病の有無
- 循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系の疾病の有無
- 先天異常の有無
- その他の疾病及び異常の有無
- 育児上問題となる事項の確認・育児相談
9~10カ月児健康診査
9~10カ月児健康診査では、身体測定、医師による診察を実施します。ハイハイやつかまり立ちなど発達の状況を確認し、喃語、歯が生えているかなどもチェックします。
9~10カ月頃は、体つきや発達状況に個人差があらわれ不安に感じる方もいるため、気になることがあれば医師や保健師に相談しましょう。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 運動発達の状況
- 精神発達の状況
- 神経系・感覚器系の異常の有無
- 血液や皮膚の疾病の有無
- 循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系の疾病の有無
- 先天異常の有無
- その他の疾病及び異常の有無
- 予防接種の実施状況
- 育児上問題となる事項の確認・育児相談
1歳6カ月児健康診査
1歳6カ月児は、母子保健法により健診を実施しなければならないと義務付けられています。1歳6カ月児健康診査では、身体測定、医師による診察、子育てに関する相談などを実施します。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 皮膚の疾病の有無
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 四肢運動障害の有無
- 精神発達の状況
- 言語障害の有無
- その他の疾病及び異常の有無
- 予防接種の実施状況
- 育児上問題となる事項の確認・育児相談
3歳児健康診査
3歳児は、母子保健法により健診を実施しなければならないと義務付けられています。3歳児は身体機能が発達し、社会性や基本的な生活習慣を身につける時期です。
3歳児健康診査では、身体測定、医師による診察、子育てに関する相談を実施し、発達状況や感覚機能等の異常の有無などを確認します。健診内容は主に以下のような項目です。
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 皮膚の疾病の有無
- 眼の疾病及び異常の有無
- 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 四肢運動障害の有無
- 精神発達の状況
- 言語障害の有無
- その他の疾病及び異常の有無
- 予防接種の実施状況
- 育児上問題となる事項の確認・育児相談
自治体によっては、乳幼児への切れ目のない母子保健の提供を目的として5歳児健診を実施しているところもあります。5歳児健診を受けることによって、社会性発達の評価、発達障害などの早期発見や育児の悩みを相談することができ、必要な専門的支援や就学時のフォローアップにつながります。
お住まいの自治体で5歳児健診を実施している場合は、ぜひ受診を検討しましょう。
乳幼児健診はどこで受けられる?
生後1カ月の健診は出産をした病院や産院で母体の健診と一緒に受けられることがほとんどです。それ以降の乳幼児健診は、お住まいの市区町村の保健センターまたは、地域の医療機関で受診します。健診の実施場所や期間などの案内は、乳幼児健診の通知に記載されています。乳幼児健診に該当する月齢・年齢が近くなると、自治体から案内が届くので内容を確認しましょう。
また、赤ちゃんは乳幼児健診だけでなく予防接種も受ける必要があります。ご自宅周辺の小児科医などでかかりつけ医を決め、そこで健診・予防接種とあわせて診てもらえると、赤ちゃんの体調不良時だけでなく気になることも相談できて安心です。
乳幼児健診の方法
乳幼児健診には「集団健診」と「個別健診」の2種類があります。集団健診は、指定された日に市区町村の保健センター等へ行き、集団で受診する方法です。個別健診は、希望する地域の医療機関へ行き、個別に受診する方法です。健診が義務付けられている1歳6カ月児健診と3歳児健診は集団健診で実施され、それ以外は個別健診で実施されるケースが多いですが、自治体によって受診方法は異なるため事前に確認しておきましょう。
乳幼児健診に関する疑問を解決!

初めて健診に行く方は、どんなものが必要なのか、費用がかかるのかなど不安もあるのではないでしょうか。ここでは、赤ちゃんの健診に関する疑問について解説します。
乳幼児健診は行かなくてはダメ?
健診を受けることにより、お子さまの隠れた病気などを早期に発見することができ、早期治療・養育につなげるうえで役立ちます。日常生活では病気に気づかないケースもあるため、必ず健診に行くことをおすすめします。
行かなかった場合、自治体の職員が健康状態を診るためにご自宅を訪問することもあります。
健診にかかる費用はすべて無料?
自治体で実施される乳幼児健診は、すべて無料です。ただし、自治体から指定されている期間外に任意で乳幼児健診を受ける場合は、費用がかかるケースもあります。任意の乳幼児健診の費用については、自治体によって対応が異なるため、確認しておきましょう。
健診のとき、何を持っていけば良い?
健診の際は以下の持ち物が必要です。
【持参が必要なもの】
- 受診票
- 母子手帳
- 健康保険証
- 乳幼児医療費受給者証(子ども医療費受給資格証) など
【持って行くと良いもの】
- おむつ
- おしりふき
- 水分補給のための水や麦茶
- おもちゃ
- 簡単に羽織れるもの など
受診票は、健診の通知とともに自治体から送付されますが、自治体によっては母子手帳交付の際に受診票の綴りをまとめた別冊を渡すこともあります。なお、自治体からの通知に健診に必要なものが記載されていますので、事前に確認しておきましょう。
また、お子さまのことで何か気になることがあれば、事前に母子手帳などに記入しておきましょう。あらかじめ気になることをメモしておくことで、健診当日にスムーズに質問することができます。
体調が悪いときはどうすれば良い?
健診の前日や当日、体調を崩してしまうこともあるかもしれません。
お子さま・保護者の方が体調を崩してしまった場合は、無理に外出すると体調が悪化する可能性や、他の方に伝染ってしまう可能性もあるため、健診は見合わせるようにしましょう。
乳幼児健診の日程は調整が可能です。受診予定の病院や市区町村の担当課に連絡をし、健診日を調整してもらいましょう。
感染症が流行しているうちは出かけるのが不安
感染症が流行していると、医療機関や集団健診に連れていくことに不安を抱くかもしれません。
保健センターや医療機関は、感染症対策を実施している場所が多いため、安心して利用できます。また、乳幼児健診は定期的にお子さまの健康状態を確認し、育児に関して相談できる大切な場所です。できるだけ適切な時期に、乳幼児健診を受けるようにしましょう。
乳幼児健診は必ず受けよう
赤ちゃんが生まれると育児に加えて乳幼児健診や予防接種などやるべきことが多く、家事が捗らないこともあるでしょう。しかし、乳幼児健診は赤ちゃんの発育状態を確認するために必要なことなので、必ず受けるようにしましょう。

大切な家族の健康と安全安心な生活を守るためには、ご自宅の防犯も強化したいものです。ALSOKでは、ご家族の非常時に備えられるホームセキュリティを「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つご用意しています。セルフセキュリティでは、お手頃価格〔月額 990円(税込)から〕でホームセキュリティを実現でき、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。オンラインセキュリティでは、不審者の侵入や火災などの異常発生時には自動でガードマンが駆けつけます。特別な訓練を積んだガードマンが、迅速かつ適切に対処し、ご家族とお住まいを守ります。
スマートフォンを持っているだけで自動で警備を解除、外出時はワンタッチで警備を開始できる機能や、窓の閉め忘れ・スマートフォンの持ち忘れのお知らせ機能もあるため、育児中で子どもに気を取られがちな毎日も安心です。
育児と家事の忙しいなかでも対策できるホームセキュリティの導入を、ぜひご検討ください。
また、ALSOKでは、忙しいママ・パパを助けるために家事代行サービスを提供しています。育児と家事の両立にお悩みの方は、ぜひ利用を検討してみてください。
まとめ
今回は、乳幼児健診についてスケジュールやよくある疑問についてご紹介しました。
乳幼児健診とは、赤ちゃんと就学前までの子どもの健康・発育状態を確認するための健診のことです。病気などの早期発見・治療につなげられるため、必ず受けるようにしましょう。また、健診では育児に関することも相談できます。ご不安なことや分からないことは、この機会に相談すると良いでしょう。