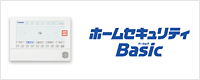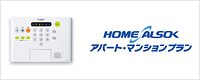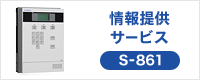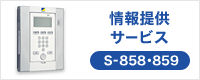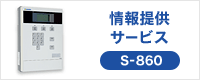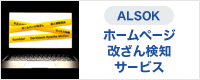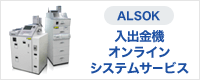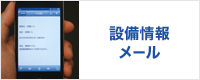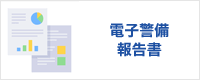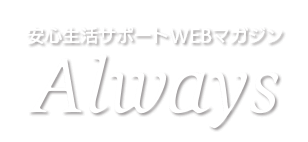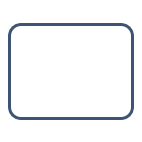山梨県東南部、郡内地方に位置する富士吉田市は、八の字の裾野を引く富士山の全景が眺められるフォトジェニックな街。
かつて織物で栄えた城下町、都留市とあわせて旅すれば、江戸時代から人々を魅了してきた「富士みち」の歴史が見えてきます。
写真提供:富士吉田市

世界中の人を惹きつける日本を代表する絶景
ある晴れた日、富士吉田市の新倉山浅間公園を訪ねました。この公園は新倉富士浅間神社の敷地内にあるため、まずは山の麓から階段を登って、神社の境内に向かいます。お参りを済ませたら、境内の脇から山の中腹へ続く長い階段を登っていきましょう。階段につけられた「咲くや姫階段」の名は、神社の御祭神で、富士山の神様でもある木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)にちなんだもの。「さくや」の名前に合わせて398段あります。ゆっくり登って15分とのことですが、途中で足が動かなくなり、息を整える人も多くいました。なんとか階段を登りきると、戦没者慰霊の五重塔「忠霊塔」があり、その背後に展望デッキが設けられています。ここから眺める富士山の見事なこと!手前に立つ忠霊塔や新倉山の木立が完璧なバランスで調和する風景は、日本を象徴する景色のひとつとして、外国人旅行者にも人気です。
新倉山浅間公園・忠霊塔
(あらくらやませんげんこうえん・ちゅうれいとう)
0555-21-1000(一財)ふじよしだ観光振興サービス
山梨県富士吉田市浅間2-4-1
見学自由

新倉山浅間公園の展望台から見る、新倉富士浅間神社の忠霊塔と富士山
写真提供:富士吉田市
江戸時代から続く富士登山の歴史を学ぶ

写真提供:(一財)ふじよしだ観光振興サービス
「人はなぜ富士山に登るのか」。ふじさんミュージアムのVRシアターでは、根源的な問いから始まる、迫力の映像が楽しめます。360度の壁と床に富士山の森、登山道や山頂が映し出され、富士登山に挑戦したことがない人も、その雰囲気をリアルに感じることができます。館内には富士登山の歴史に関する展示も多く、江戸時代に富士山信仰が広まった背景や庶民が富士登山に出かけた「富士講」の仕組み、登山者を自宅に宿泊させ、祈祷や登山の世話をした「御師(おし)」についても紹介しています。
富士講の人々は日本橋から吉田まで120kmの道のりを3~4日かけて歩きましたが、彼らが歩いた道が残っているのも興味深い点です。山梨県大月市から富士吉田市に続く古道は「富士みち」とよばれ、富士講の人々が立ち寄ったとされる、寺社や旧跡があちこちにあります。
下吉田の「富士みち」沿いにある本町の商店街は、正面に富士山が見られることから、SNSで人気に火がつきました。この商店街で立ち寄ったのが「LONGTEMPS」です。1934(昭和9)年に家具店としてスタートし、現在は家具とインテリア雑貨、洋服などを扱っているとのこと。特にイギリス、北欧のアンティーク家具やヴィンテージ家具の中には、リーズナブルな掘り出しものが多いため、わざわざ遠方から買いに来る方もいるそうです。また、富士吉田は繊維業が盛んなため、地元のファクトリーブランドの商品も充実しています。1点ものの洋服やリネン類、布小物などおしゃれな商品ばかりで、雑貨好きにはたまらない空間です。
商店街を富士山に向かって進むと「金鳥居(かなどりい)」。この先は神様の領域とされており、「御師」の宿坊が並びます。富士講の人たちはここで宿泊し、お祓いを受けて登山に向かいました。
ふじさんミュージアム(ふじさんみゅーじあむ)


0555-24-2411
山梨県富士吉田市上吉田東7-27-1
9:30~17:00
大人400円(御師旧外川家住宅との共通入館券)
*御師旧外川家住宅、富士山レーダードーム館との共通入館券は800円
火曜


LONGTEMPS (ろんたん)

0555-22-0400
山梨県富士吉田市下吉田3-12-54
10:00~19:00
火曜




温泉でほっこり
吉田のうどんを食べる至福
かつて富士講の人たちは、富士山の湧き水が流れる川や滝で水行を行いながら、富士みちを歩きました。その点、現代を生きる私たちは幸せです。車や電車で富士山を見ながら移動でき、温泉にまで入れるのですから。
絶叫マシンで有名な「富士急ハイランド」の隣にある、「ふじやま温泉」は全国的にも珍しい「マグネシウム・カルシウム・ナトリウム‐炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉」という、すべての泉質の温泉がブレンドされた天然温泉で、美肌の湯として人気です。樹齢200年超えのケヤキの大木を柱に据えた「純木造浴室」は、釘を使わない伝統工法で梁が組まれており、レトロな雰囲気のなかで良質のお湯を楽しめます。お風呂上がりには、3階の展望休憩室や4階の岩盤浴スペースへ。美しい富士山を眺めてくつろぐ、至福の時間を過ごせます。
温泉を楽しんだ後は、「吉田のうどん」を食べに出かけました。吉田のうどんは富士吉田市や都留市を含む郡内地方の伝統食です。この地域では古くから織物産業が盛んで、江戸時代以降は「郡内織」とよばれる織物が富士みちを通って江戸へと出荷されていました。機織りに忙しい女性に代わって、男性が昼食の用意をするようになり、太く、コシの強いうどんが生まれたといわれています。
都留市の「山もとうどん」は、遠方からも多くの人が訪れる人気店です。主人の酒井建一さんが打つ麺は、うどんの概念をくつがえすほどの太さと長さ。食べ応え満点の麺をひと口噛めば、小麦の香りと味が一気に広がり、醤油と味噌のコクのある出汁、まろやかな卵と混然一体に。「肉うどん」に馬肉が使われ、キャベツがのせられているのも吉田のうどんならではです。唐辛子ベースの薬味「すりだね」と天かすで、好みの味を作りながらいただきましょう。
ふじやま温泉 (ふじやまおんせん)

0555-22-1126
山梨県富士吉田市新西原4-17-1
朝風呂6:30~9:00、10:00~23:00(最終入館は22:00)
大人1600円(土・日曜、祝日は2000円、ただし朝風呂は全日800円)、岩盤浴は別途680円
不定休



山もとうどん(やまもとうどん)

0554-45-8733
山梨県都留市古川渡397-1
10:30~14:00
火・水曜


人気を集めた郡内織
郡内地方は寒冷な気候で、山間のため平地が少ないことから稲作に向かず、古くから養蚕や絹織物の生産が行われていました。江戸時代、谷村藩の藩主となった秋元泰朝は絹織物の振興に努め、高品質な郡内織は江戸でも評判を集めるように。谷村の城下町(現都留市)は、郡内織の流通拠点として栄えました。